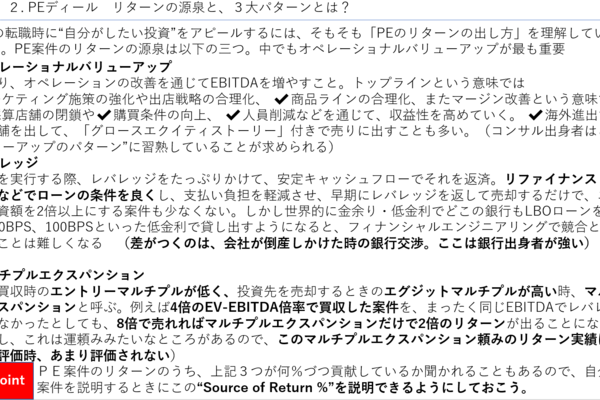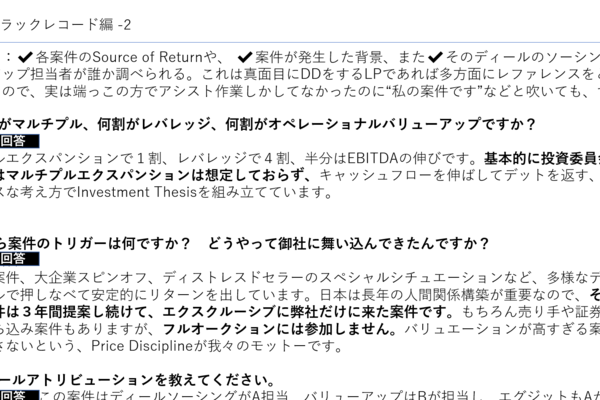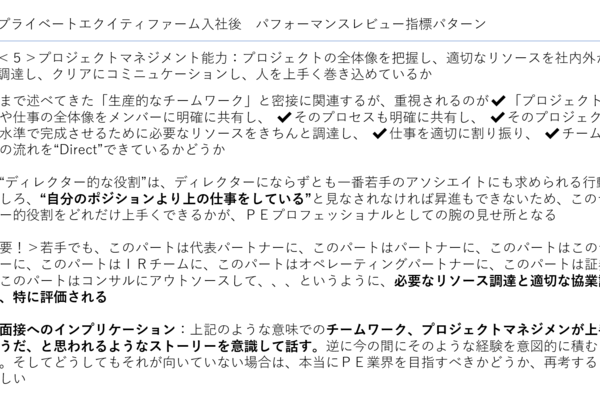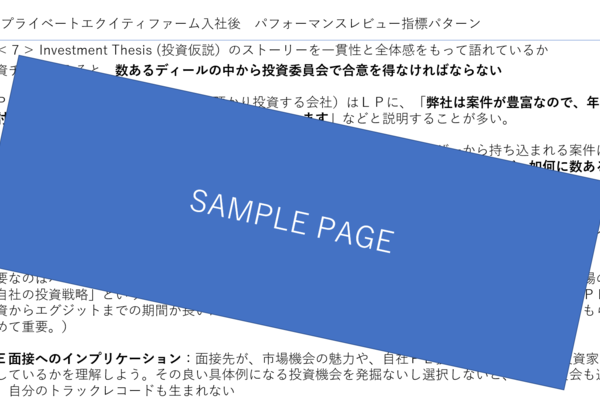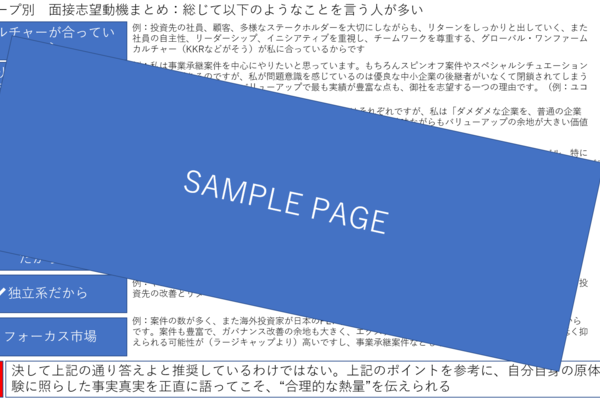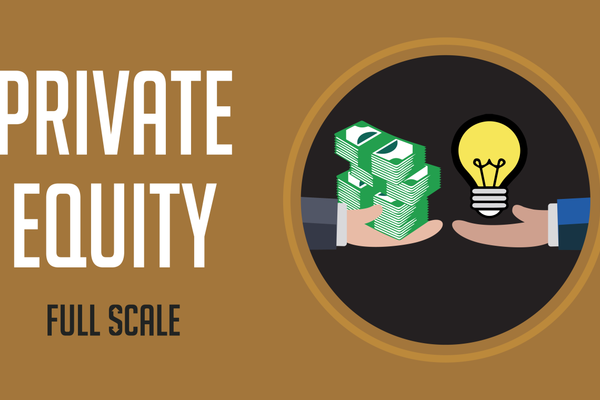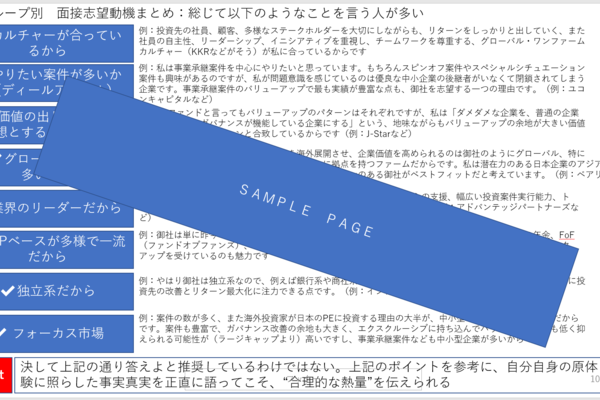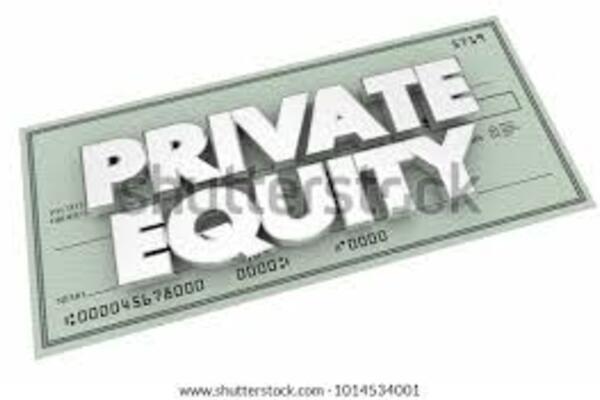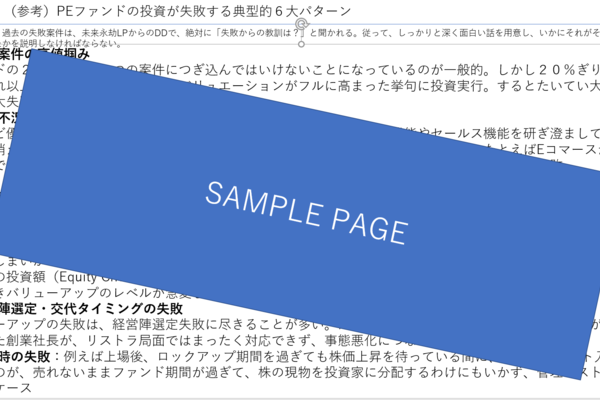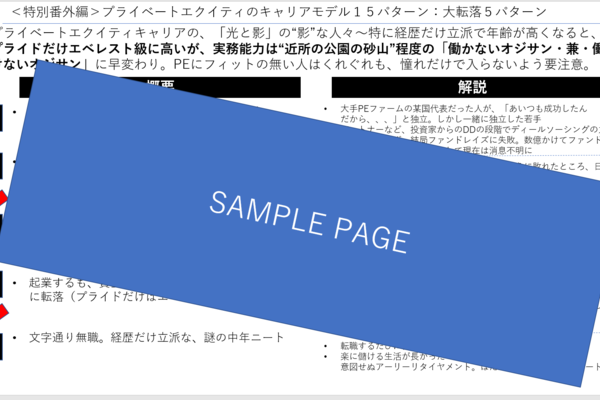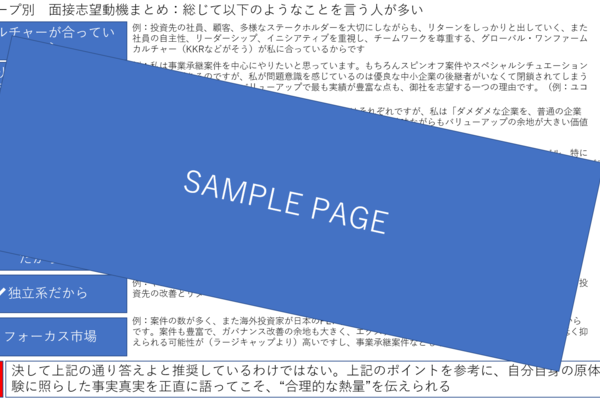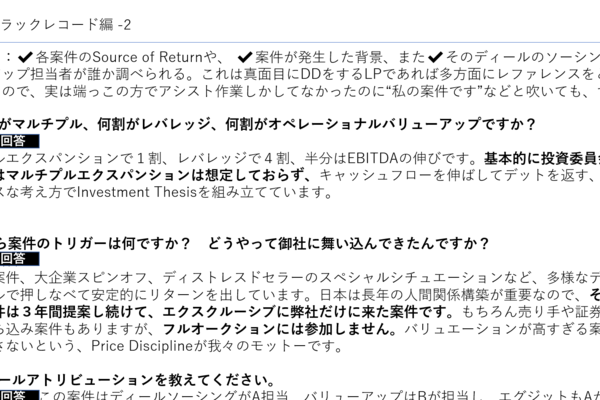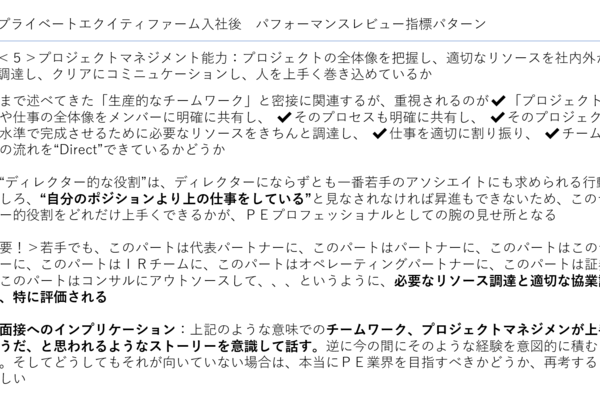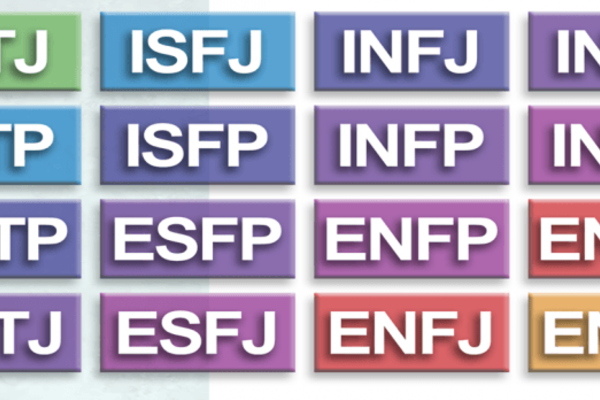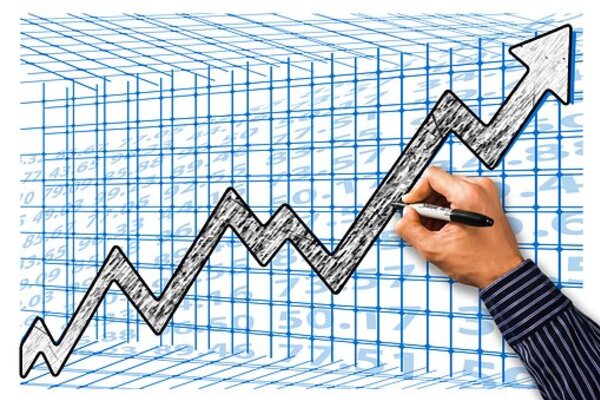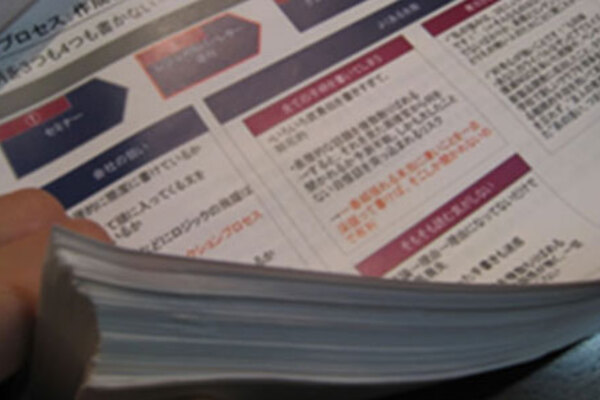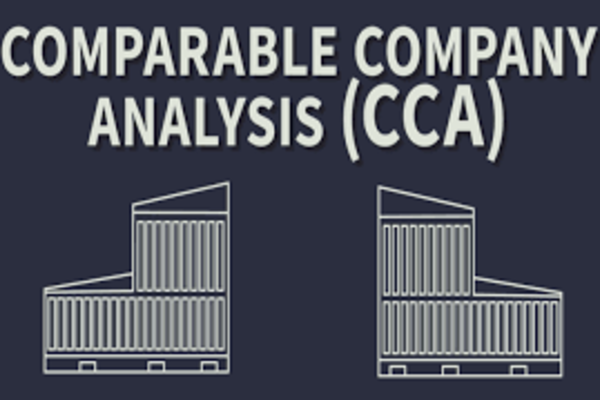コンサル、外銀からスタートアップへのCXO入社や、起業をする人が増えている。
ニュースやSNSではその成功例ばかりが取りざたされるが、その裏で失敗した人々のポンコツ起業の瓦礫の山が築かれていることは、あまり語られない。私も様々な同僚が、様々な怪しげな会社を立ち上げては、無残に沈没していく様を数多く見てきた。
以下では...

ニュースやSNSではその成功例ばかりが取りざたされるが、その裏で失敗した人々のポンコツ起業の瓦礫の山が築かれていることは、あまり語られない。私も様々な同僚が、様々な怪しげな会社を立ち上げては、無残に沈没していく様を数多く見てきた。
以下では...