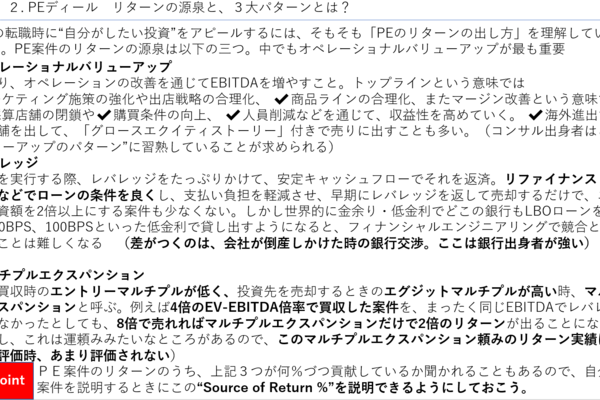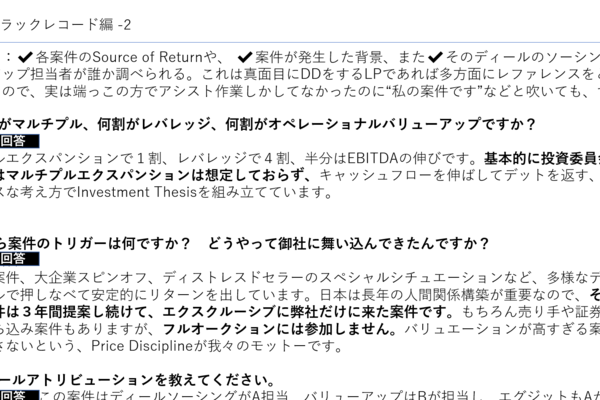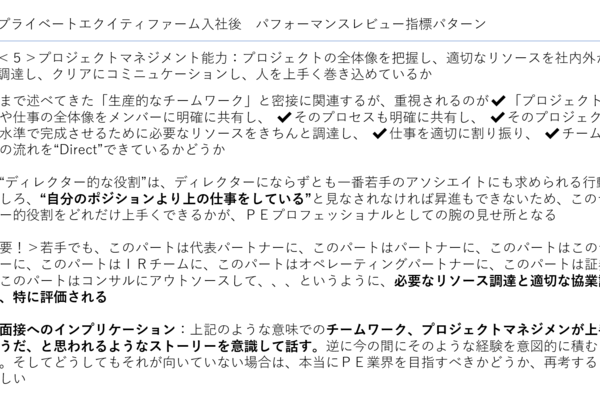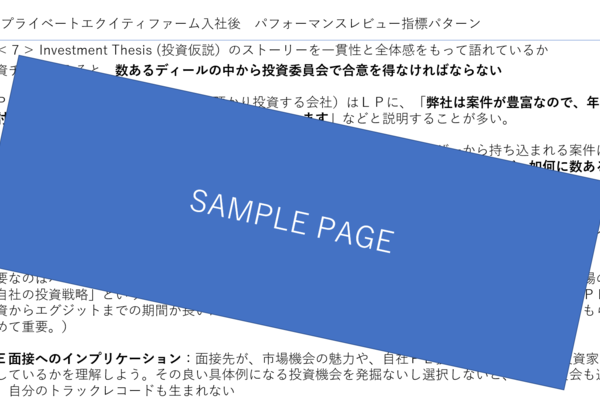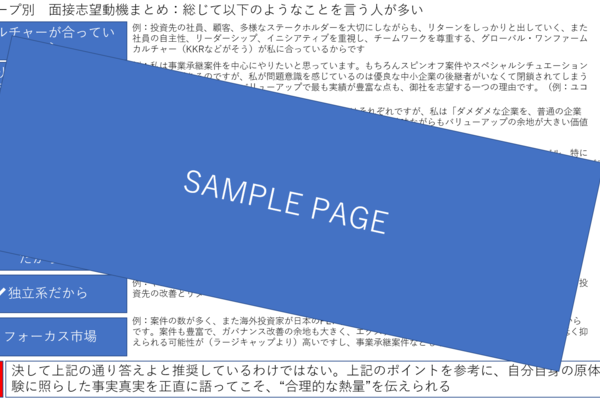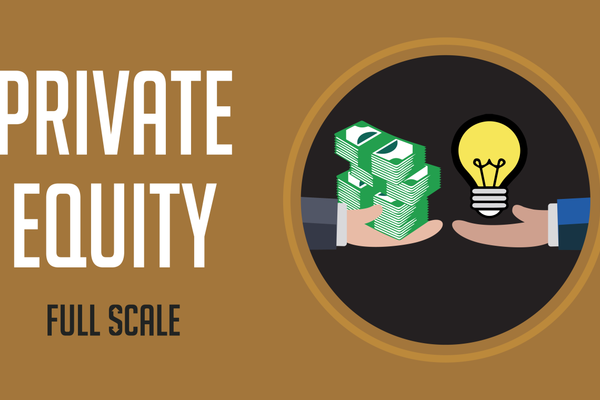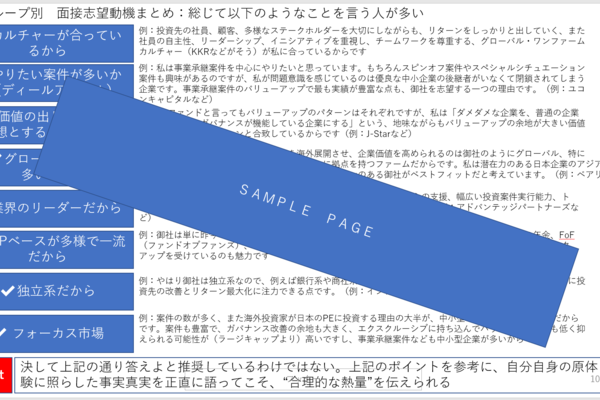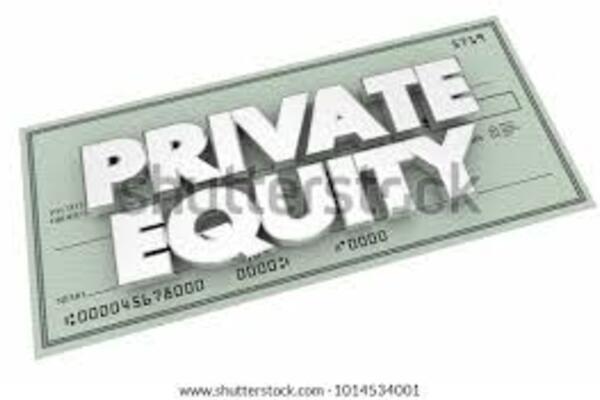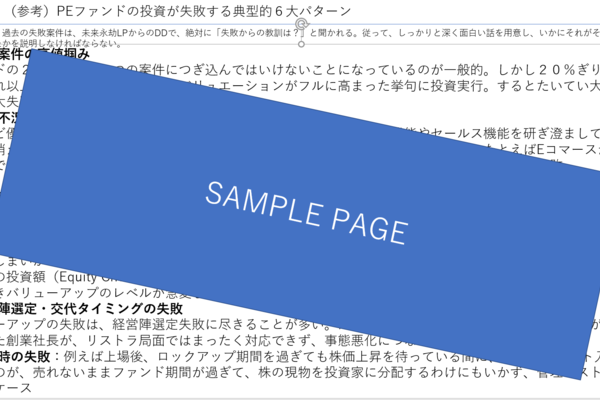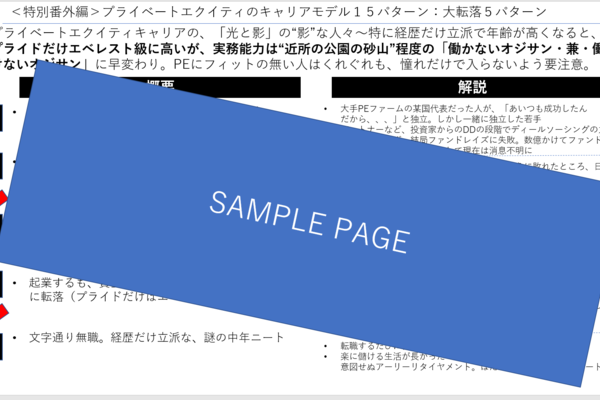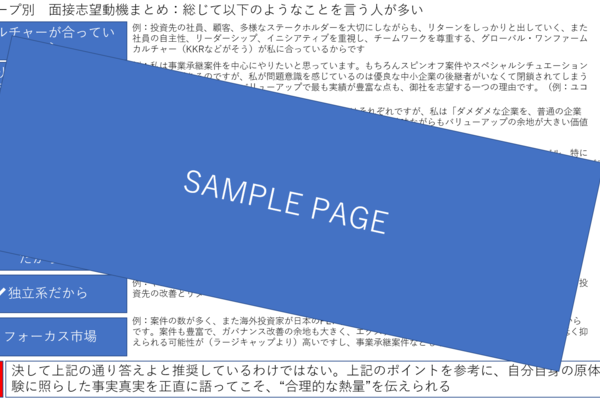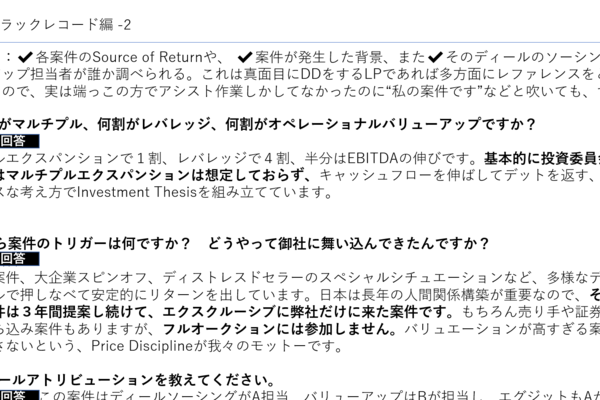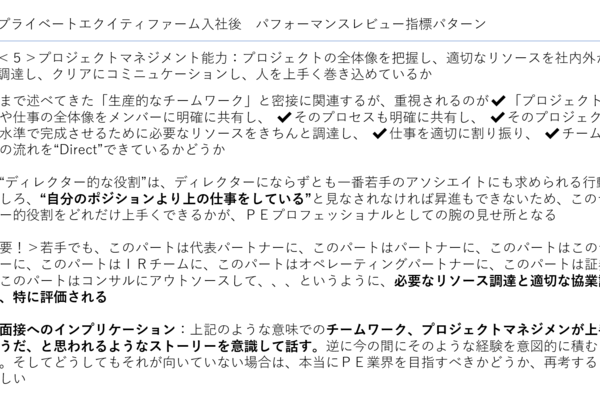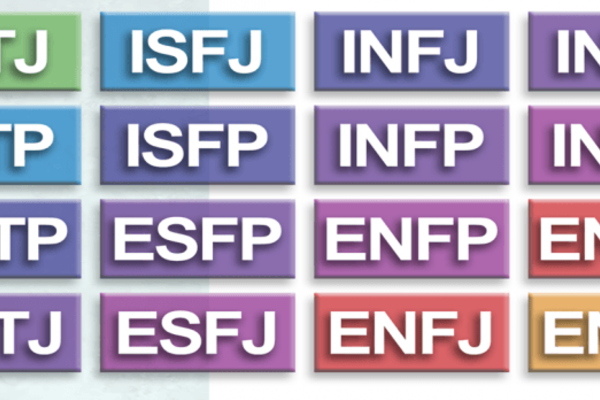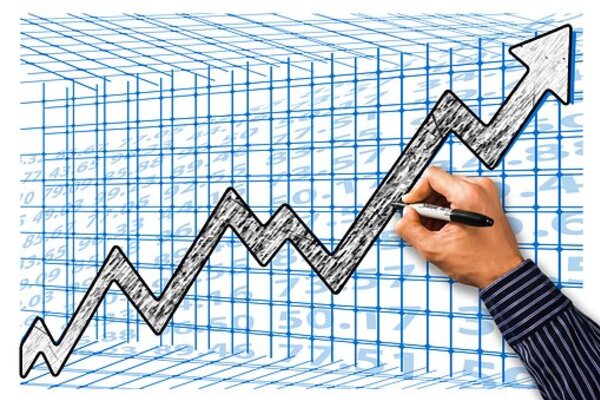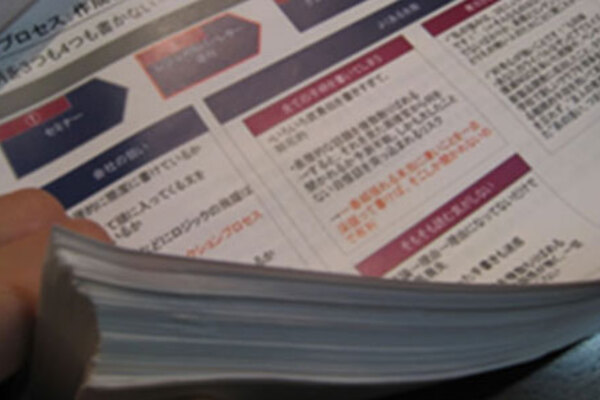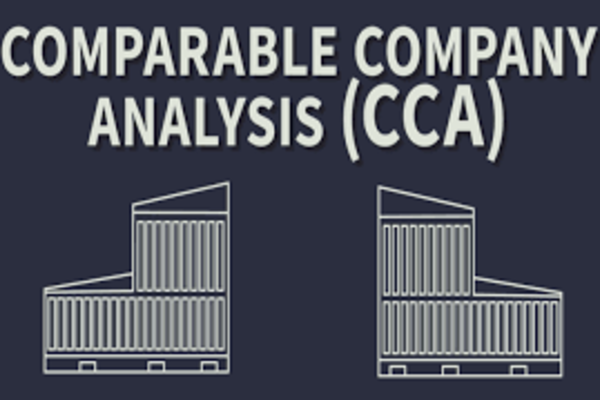-
1
位
-
2
位
-
3
位
-
4
位
-
5
位
-
6
位
-
7
位
-
8
位
-
9
位
-
10
位
-
11
位
-
12
位
-
13
位
-
14
位
-
15
位
-
16
位
-
17
位
-
18
位
-
19
位
-
20
位
-
21
位
-
22
位
-
23
位
-
24
位
-
25
位
-
26
位
-
27
位
-
28
位
-
29
位
-
30
位
-
31
位
-
32
位
-
33
位
-
34
位
-
35
位
-
36
位
-
37
位
-
38
位
-
39
位
-
40
位
-
41
位
-
42
位
-
43
位
-
44
位
-
45
位
-
46
位
-
47
位
-
48
位
-
49
位
-
50
位
-
1
位
-
2
位
-
3
位
-
4
位
-
5
位
-
6
位
-
7
位
-
8
位
-
9
位
-
10
位
-
11
位
-
12
位
-
13
位
-
14
位
-
15
位
-
16
位
-
17
位
-
18
位
-
19
位
-
20
位
-
21
位
-
22
位
-
23
位
-
24
位
-
25
位
-
26
位
-
27
位
-
28
位
-
29
位
-
30
位
-
31
位
-
32
位
-
33
位
-
34
位
-
35
位
-
36
位
-
37
位
-
38
位
-
39
位
-
40
位
-
41
位
-
42
位
-
43
位
-
44
位
-
45
位
-
46
位
-
47
位
-
48
位
-
49
位
-
50
位