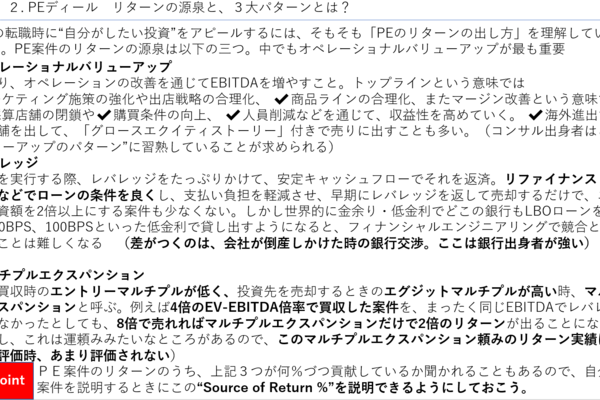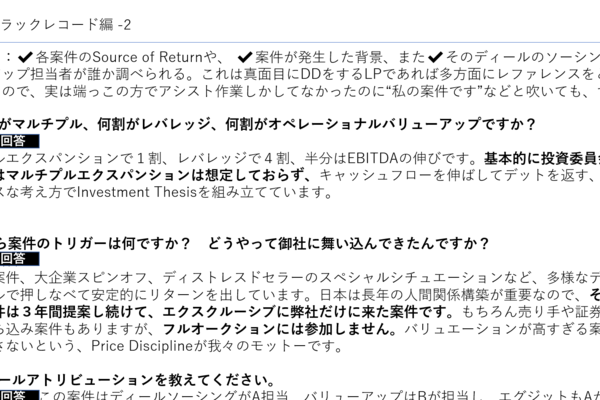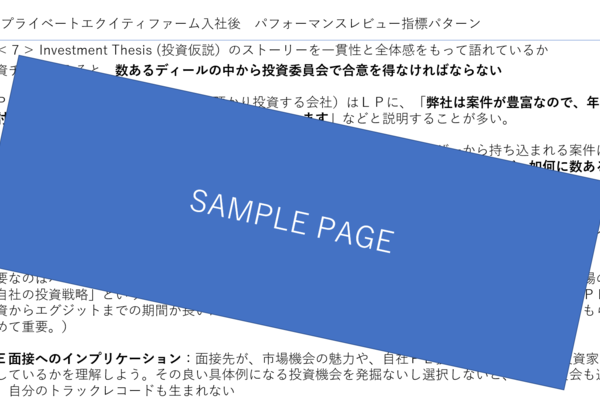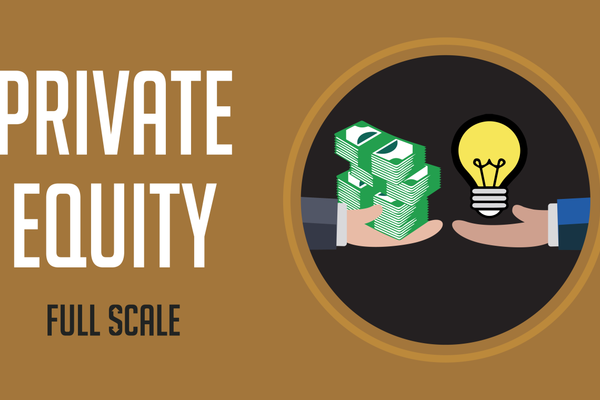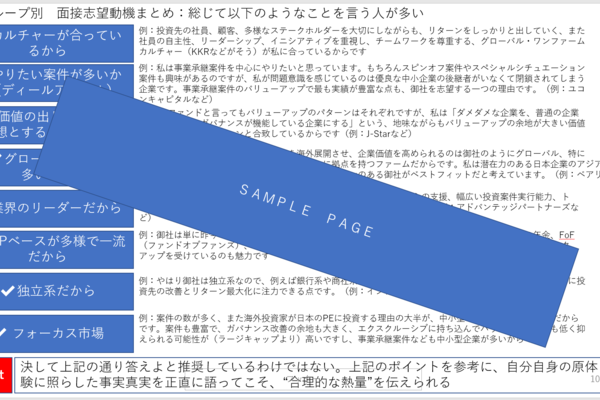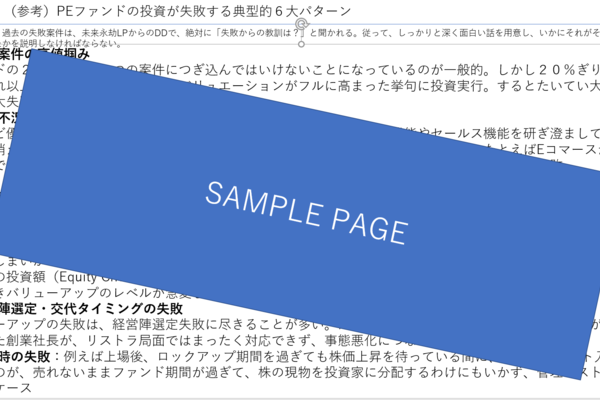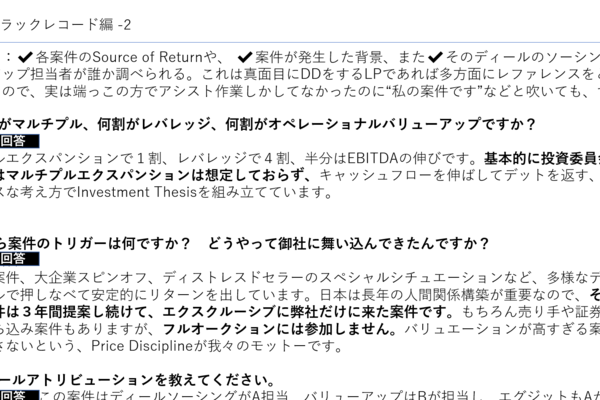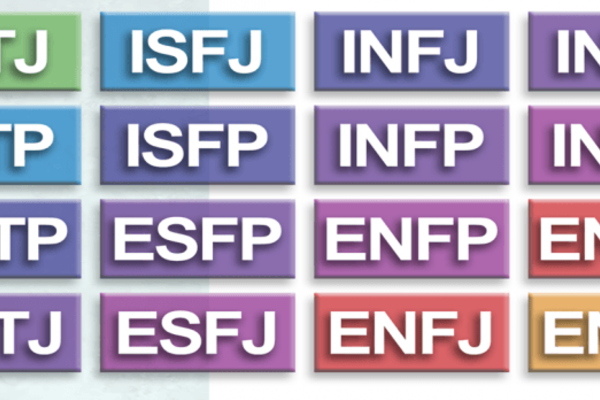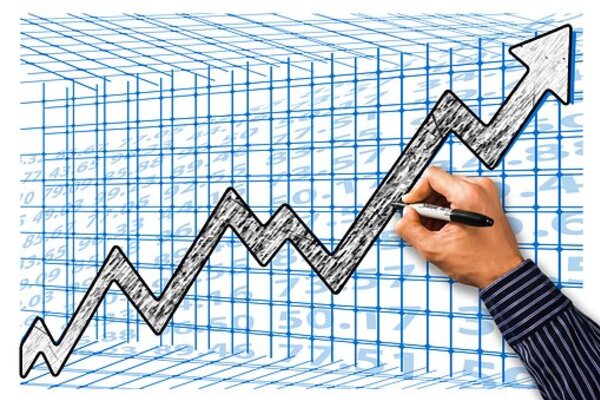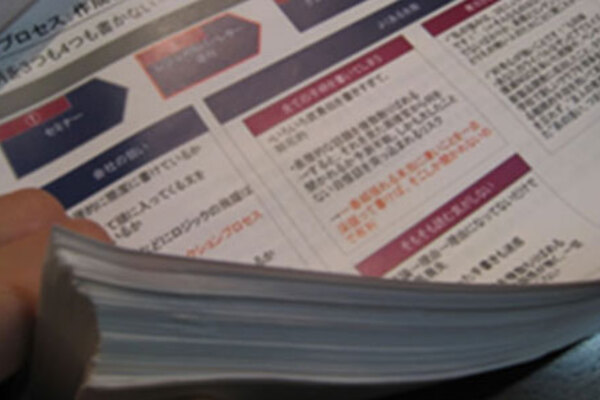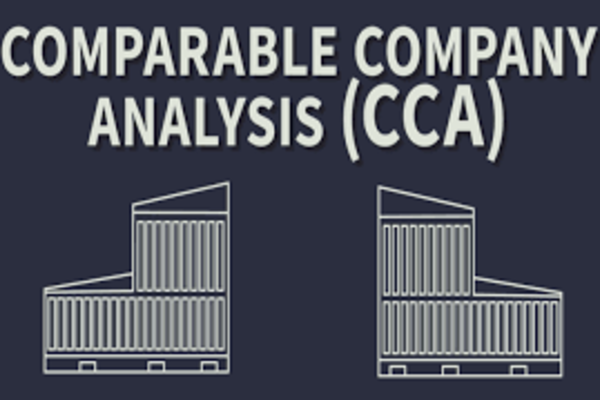野村総研大特徴とは?
日系コンサルティングファームのトップファーム、野村総研の特徴を以下に記載します。
自由でフラット
野村総研は、野村証券の調査部と、野村のシステムコンサルティング会社が一緒になってできた会社です。
野村という響きに連想される厳しい上下関係や体育会系カルチャーは強くなく、...

日系コンサルティングファームのトップファーム、野村総研の特徴を以下に記載します。
野村総研は、野村証券の調査部と、野村のシステムコンサルティング会社が一緒になってできた会社です。
野村という響きに連想される厳しい上下関係や体育会系カルチャーは強くなく、...